【14年という長きに渡る戦いに終止符を打てた理由】
R6年度電験2種二次試験がR6年11月10日(日)に実施されたわけですが、
この二次試験に不合格になると振り出しに戻る予定でありました。
訳あって、R7年度にまで二次試験受験資格を延伸できたわけですが、
その資格を行使することなくなんとか幸いにも合格できました。
14年間、一次試験に合格するも二次試験には不合格になるということが
幾度となく繰り返されてたせいか、今回のR6年度二次試験も合格するという
自信がほとんどありませんでした。
メンタル面もさることながら、実際に試験直前期にあっても停電作業などの
業務が数多くあり、とてもじゃないが電験2種に集中できる環境とは言えませんでした。
そんな愚痴をこぼしていても何の解決にもなりませんでしたが、本当だから
仕方がありません。
とは言うものの、心のどこかに受かりたい!という気持ちはあったのは確かで
それが証拠に、仕事がひと段落した試験直前の2週間は「どうやったら二次試験に
合格できるだろうか?」という戦略を必死に考えていたのです。
必死に考えた結果、私の合格戦略として、
・「塚崎ゼミで取り扱われた問題」を復習すること
・試験本番では「論説問題」をないがしろにしないこと
が立案されたわけです。
残された2週間をこの戦略に基づいて、学習していくことにしました。
塚崎ゼミでは、計算問題と論説問題の両方を取り扱った過去問を題材として
講義されていて、当時参加したゼミナールの板書ノートがありましたのでそれを
学習に使用しました。
ここでは、『試験本番では「論説問題」を捨てない』という考えを基に、計算問題も論説問題も両方とも学習をしていきました。
実際の学習方法は、自力解答と自力解答ができなかった場合は板書ノートの写経を実践していきました。
また、直近に出題された過去問についても、計算問題と論説問題を分け隔てることなく学習を進めました。
このようにして、あっという間の2週間が過ぎていよいよ試験当日を迎えることになりました。
試験当日は、緊張感もありながら、しかしどこかしら落ち着いていた感じもありました。
電験2種二次試験は、どんな問題が出題されるかなんて全く想像がつかないわけですが、試験本番における戦略として考えていたこととしては、
・選択する問題をまずは決める
・次に、問題を解く順序を最初に決めておく
・(電力管理科目において)論説問題をなるべく始めの段階で解いておく
・(機械制御科目において)自動制御はなるべく避けて「機械2問」で勝負する
などがありました。
R6年度の電力管理科目は6問中4問が論説問題というイレギュラーな年度となりました。
私は3問を論説問題、そして1問を計算問題という選択にしました。
また、機械制御科目では、当初機械2問でやろうと目論んでいたわけですが、1問目の同期機がイマイチ自信が持てなかったことがあり、1問目の選択を辞めて2問目の変圧器と4問目の自動制御を選択せざるを得ない状況となったわけです。
これは完全に想定外の出来事となりました。
最後の最後まで、自動制御だけは解ける自信が持てなかったこともあり、苦渋の決断で4問目の自動制御を選択したのを覚えています。
しかし、とは言え自動制御に関しては、十分に今まで学習を続けてきたことも幸いして、全問正解とはいきませんでしたが6割以上は解くことができました。
続けていると少しは良いこともあるもんだと、このときばかりは思わざるを得ませんでした。
また、電力管理科目に関しては、論説問題優位の年度であったことが幸いして、当然論説問題を中心に選択して解いていきました。
1問だけ計算問題を選択しましたが、4問目の計算問題を選択しました。
ところが、この計算問題を見ると問題文章量が非常に多いのに面食らってしまいました。
したがって、4問目の計算問題は一番最後に解くことに決定して、論説問題の3問をまずは解いていくことになりました。
1問目が火力発電からの出題、2問目が変電からの出題、6問目が分散型電源からの出題ということで、まずはこの3問を何とかして解いていくという戦略に決定しました。
この3問を解く際に、「論説問題を捨てない」という言葉を思い出して、さらにこの言葉を強力なものに変換して「論説問題で勝負する」という言葉としました。
この言葉を胸に、わかっていることをとにかく少しでも文章にしたためていきました。
このようにして何とか論説問題をあらかた解いてから残りの4問目の計算問題に着手しました。
小問が3つの構成となっておりましたが、やはり文章量が非常に多いのは面倒でした。
しかし、解かないと落ちてしまうので、問題文を読み進めると小問をはじめから解く必要がないことに気が付きました。
したがって、問4の解く順序としては、
・小問(3)をまずは解く ⇒短絡電流を求める問題でした(自宅での演習を十分にしていた)
・次に小問(1)を解いてみる ⇒やってみると非常に簡単な問題でした
・小問(2)はパス ⇒ 時間がありませんでした
こんな感じで何とか粘りに粘って、電力管理の試験時間をフルに使って試験問題を解いていきました。
機械制御科目では、問2の変圧器と問4の自動制御を選択し解いていきました。
解答順序としては、問2⇒問4の順番でした。
問2の変圧器の問題は過去問の類似問題ということで、解けそうでしたが試験場の緊張感もあり、なかなか解答をしたためることができませんでした。
それでも何とか、満点ではなかったものの小問(4)以外は完答できました。
問4については、自動制御でしたがもうこれはやるしかありませんでしたので必死でした。
時間が少ない割に計算量はかなりあるし、本当に必死でした。
自動制御は当初選択するつもりはなかったものの、学習においては十分に演習を積んできたことが幸いして、ある程度は解けたことが合格にもつながったと考えています。

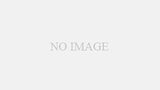
コメント